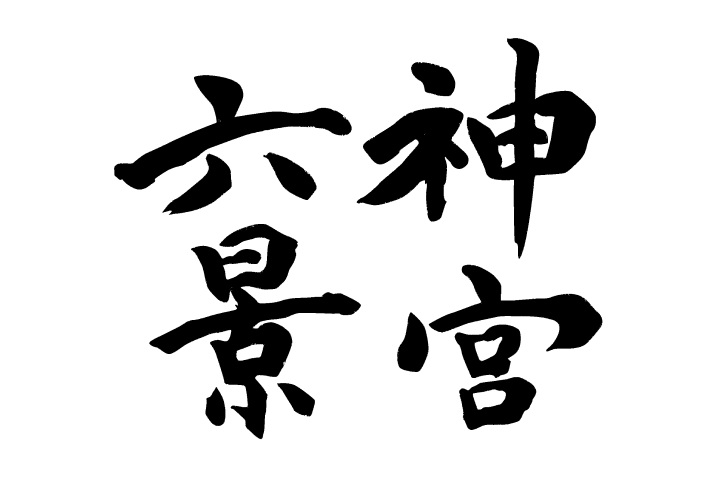私は、明大OBの河村実義先生、川口啓太先生、亜大OBの磯口洋成先生らが指導した江戸川学園取手高校に入学しました。当初は帰宅部でしたが、姉の担任だった野球部顧問の熱心な誘いにより、途中から野球部に入部しました。甲子園を目指せるようなチームではありませんでしたが、神宮球場で亜大の試合を観たことで、「大学で野球を続けたい」と思うようになりました。
早大を志したきっかけは、平成2年春の優勝と、平成4年春に大森篤さんが首位打者を獲得した新聞記事を見たことです。高3秋から浪人時代にかけて神宮球場に何度も通い、ガイドブックに載る先輩方の名前や出身校を覚えました。
早大野球部には捕手として入部しましたが、2年生に上がる直前に監督室に呼ばれ、着任間もない佐藤清監督から「明日からマネージャーをやってくれ」と言われました。自分がこのチームに貢献するには、選手ではなく裏方としての活躍なのだろうと思い、その日をもって選手を引退しました。
2年生マネージャーとしては毎朝、寮1階のトイレ清掃や監督のスパイク磨きのほか、あらゆる動きをして仕事を覚え、相田暢一先輩理事(当時)から可愛がっていただきました。またネットや携帯も未発達な時代、学生向け広報誌に記事を投稿して神宮球場への来場を呼びかけたり、残ったパス券は手紙を書きまくり電話をかけまくってさばき、OBの力も借りて収入を5割増にしました。また推薦入学希望者にはSPIの解説、小論文の添削、模擬面接を行い、全員合格につなげました。
4年間で優勝には届きませんでしたが、6校の同期たちとは今も連絡を取り合っています。人生においてかけがえのない仲間です。
卒業後、亀田健先輩理事(当時)から連盟の公式記録員を打診され、以来40季に亘り、この任務を続けています。歴代の早大OB公式記録員は、飛田穂洲、小川正太郎、中島治康といった野球殿堂入りの大先輩方がおり、私は10人目。飛田氏の19年を超え、早大OBとしては最長となりました。
これからも選手のプレーに敬意を払い、ルールを守り、スコアシートを読む皆さまにとって読みやすい丁寧な記録と、公平なジャッジを心がけていきます。
また健康である限り、これからも東京六大学野球を支え、盛り上げていきたいと思っています。